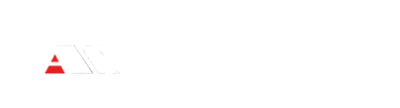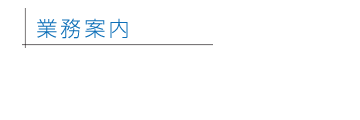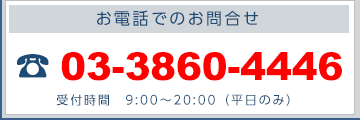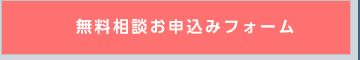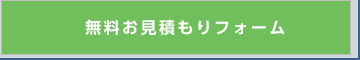■土地分筆登記
・遺産相続や相続税が発生し遺産分割や物納で土地を分けたい場合
・共有名義の土地を分割して単有名義にしたい場合
・土地の一部が別地目に変更した場合
・同じ土地に建物を建築、別名義にして融資を受けたい場合
・建物建築に伴い、道路後退により幅員を確保したい場合
土地分筆登記とは、登記された一筆の土地を分割して数個の土地を創設する登記をいいます。
一筆の土地の一部を分割して売買や融資を受けたい、あるいは遺産相続や相続税が発生し遺産分割や物納で土地を分けたい等の場合に土地分筆登記が必要なります。
土地分筆登記を申請する前提として境界確定測量を実施し正しい面積を算出し、コンクリート杭や金属標などの永久的な境界標の設置も必要です。
この登記は、申請主義により所有者の自由意思によってのみされる登記ですから、所有者に申請義務はありません。
しかし、土地の一部が別地目になった場合は、土地地目変更登記を有することから、土地の所有者は、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に土地一部地目変更・分筆登記を申請義務があります。この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)
登記費用
当事務所では常に依頼者様の立場に立ち、業務の効率化を図り、高品質の成果をより負担軽減された形でご提供いたします。
土地地積更生登記の費用は、一般的な例(1筆で200m²くらいの土地の場合を2筆に分ける)で、総額約8万円~となります。
なお、土地の大きさや現地の状況、必要書類の有無などにより大幅に変わってきますので、詳細はメール又はお電話などでご相談下さい。なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
※上記費用には、官公署等での調査業務、登記申請書類作成および登記申請、登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本)の取得までを含みます。
※上記費用には別途消費税がかかります。
※土地地積更生登記については、この費用以外に境界確定測量の費用がかかります。
必要書類
- 委任状
土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。 - 境界確認書
境界確定測量の段階で隣接地所有者との間で取り交わす書面です。
※法務局によっては、境界確認書に印鑑証明書の添付が必要になる場合があります。
※申請地が道路、里道、水路、河川等に接する場合は官民境界確定図が必要になります。 - 地積測量図
登記する土地の位置、形状及び大きさを明確にした図面です。
土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。
手続きの流れ
何らかの事由で土地を分割したい場合、土地分筆登記の申請義務があります。土地家屋調査士が依頼を受けて代理人として登記申請を行います。
![]()
当事務所に土地地積更生登記の手続きのご相談又はご依頼を頂きます。その際に、できるだけ詳細な内容をお伝えして頂ければ、回答する上での参考になり、より正確なお見積りをご提示できます。なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
![]()
ご相談内容に応じ、土地分筆登記に必要な書類をお預かり致します。
![]()
法務局、官公署等での資料調査を行います。具体的には、お預かりした資料をもとに、土地の所在地を管轄する法務局において、土地及びの登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図等を取得し、土地の概要等の確認をします。必要によっては、市区町村役場や都税事務所等での調査も必要となります。
![]()
境界確定測量により、その土地の面積を確定し、隣接土地所有者様と境界確認書を取り交わします。
![]()
資料調査・現地調査・測量をもとに、土地分筆登記の申請書・調査報告書等の登記申請書類を作成します。
![]()
必要書類がすべて揃い、土地地積更生登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ土地分筆登記の申請を致します。
![]()
法務局へ行き登記完了証を受け取ります。法務局の混雑状況や登記官の調査によりますが、通常は、登記申請から7日から10日程度で土地分筆登記は完了します。ただし、境界確定測量後土地分筆登記を申請しますので、全行程で2~4ヶ月前後の期間が必要となります。
![]()
申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。
■土地地目変更登記
・宅地として使用している土地を、建物を取り壊して道路や駐車場にした場合
土地地目変更登記とは、人為的な土地の利用方法の変更又は土地の自然的な変化によって、法定された他の地目となった場合に登記記録の登記事項「地目」内容も同じように変更する手続きのことをいいます。
地目は、その土地の主たる利用目的に応じて23種類に分類されています。(不動産登記規則第99条)
「田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地」
不動産登記法上でも、地目を定める場合には土地の現況及び利用状況に重点を置くこととされています。(不動産登記事務取扱手続準則第68条)
建物がある土地は地目「宅地」、駐車場は地目「雑種地」と、土地の現況に合わせて地目は決まります。
不動産の取引に使われる物件概要書などでも、登記簿地目と現況地目の欄がそれぞれ作られ、これがない場合は登記簿と現況が一致、あるいは現況が優先されています。また、土地の価格評価や課税についても、あくまでも現況により判断されます。
※土地地目変更登記は注意点が2つあります。
農地を農地以外の土地に変更や、売買などは、農地法という法律があるため、農業委員会に届出または許可が必要になります。
農地法でいう「農地」は、登記簿上の地目とは関係なく、「現況」で判断されます。登記簿上「雑種地」でも、農業を利用目的とした用途であれば、現況は「田または畑」です。
土地の一部が別地目となった場合は、土地地目変更登記だけでなく、併せて土地分筆登記も申請も必要になります。
理由は登記記録上一筆の土地には1個の地目のみ記載だからです。
この場合「土地一部地目変更・分筆登記」という1件の申請で登記することが可能です。
土地地目変更登記のみの場合、測量作業は必要ありませんが、同時に土地分筆登記が必要な場合は境界確定測量が必要になります。
土地の所有者は、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に土地地目変更登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第37条第1項)
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)
なお、登記手続き上の錯誤(間違い)などにより、土地の現況と登記簿上の土地の表示とが合致していない場合は、土地地目更正登記を行い、現況に合わせた表示に「更正」することができます。変更登記が「後発的に生じた不一致」なのに対し、更正登記は「当初からの誤り又は遺漏」ということになります。
登記費用
当事務所では常に依頼者様の立場に立ち、業務の効率化を図り、高品質の成果をより負担軽減された形でご提供いたします。
土地地目変更登記の費用は、単独依頼の場合、一筆約3万円~となります。
現況が農地で農地法の手続きが必要になる場合、一筆約5万円~となります。
建物表題登記と同時に登記申請する場合、調査の負担などが軽減するため、一筆約3万円~となります。
なお、土地の大きさや現地の状況、必要書類の有無などにより大幅に変わってきますので、詳細はメール又はお電話などでご相談下さい。なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
※上記費用には、官公署等での調査業務、登記申請書類作成および登記申請、登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本)の取得までを含みます。
※上記費用には別途消費税がかかります。
必要書類
- 委任状
※ご住所の変更がある場合は住民票が必要になります。
※現状の地目が農地(田・畑)である場合には、農地転用受理通知書または農地転用許可書などが必要になります。
手続きの流れ
土地の現況および利用目的が変更した場合、土地地目変更登記の申請義務があります。土地家屋調査士が依頼を受けて代理人として登記申請を行います。
![]()
当事務所に土地地目変更登記の手続きのご相談又はご依頼を頂きます。その際に、できるだけ詳細な内容をお伝えして頂ければ、回答する上での参考になり、より正確なお見積りをご提示できます。必要によっては、農地転用手続きや分筆登記が必要もあるので、ご相談下さい。なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
![]()
ご相談内容に応じ、土地地目変更登記に必要な書類をお預かり致します。
![]()
法務局、官公署等での資料調査を行います。具体的には、お預かりした資料をもとに、土地の所在地を管轄する法務局において、土地及びの登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図等を取得し、土地の概要等の確認をします。必要によっては、市区町村役場や都税事務所等での調査も必要となります。
![]()
調査資料をもとに現地調査を実施、地目が変更していると認定できるかの判断をします。現況によっては、農地転用の手続きや分筆登記が必要になることもあります。
![]()
資料調査・現地調査(・測量)をもとに、土地地目変更登記の申請書・調査報告書等の登記申請書類を作成します。
![]()
必要書類がすべて揃い、土地地目変更登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ土地地目変更登記の申請を致します。
![]()
法務局へ行き登記完了証を受け取ります。法務局の混雑状況や登記官の調査によりますが、通常は、登記申請から7日から10日程度で土地地目変更登記は完了します。ただし、農地法上の手続きが必要な場合は期間が必要となる可能性があります。
![]()
申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。
■土地地積更生登記
・分筆登記の際に、分筆前の土地の登記簿地積が相当でない場合
・相続税の物納をする場合
土地地積更正登記とは、登記簿に記載されている土地の表示事項が、登記された当初から誤った地積で登記されている場合若しくは遺漏している場合に、現況面積と登記記録上の面積を合致させる登記をいいます。
土地地積更正登記を申請する前提として境界確定測量を実施し正しい面積を算出し、コンクリート杭や金属標などの永久的な境界標の設置も必要です。
明治から昭和時代、測量精度が原因で登記簿面積と実測面積に差が生じるケースが数多く見受けられます。このような不一致を、地積更正登記によって解決できます。
土地地積更正登記は、登記手続き上の錯誤や遺漏等により、現況と登記簿上の土地の表示が合致していない場合に、現況に合致する表示に「更正」する登記で、この登記は、申請義務規定もないため、所有者に申請義務はありません。
登記費用
当事務所では常に依頼者様の立場に立ち、業務の効率化を図り、高品質の成果をより負担軽減された形でご提供いたします。
土地地積更生登記の費用は、一般的な例(1筆で100m²ぐらいの土地の場合)で、一筆約5万円~となります。
なお、土地の大きさや現地の状況、必要書類の有無などにより大幅に変わってきますので、詳細はメール又はお電話などでご相談下さい。なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
※上記費用には、官公署等での調査業務、登記申請書類作成および登記申請、登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本)の取得までを含みます。
※上記費用には別途消費税がかかります。
※土地地積更生登記については、この費用以外に境界確定測量の費用がかかります。
必要書類
- 委任状
土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。 - 境界確認書
境界確定測量の段階で隣接地所有者との間で取り交わす書面です。
※法務局によっては、境界確認書に印鑑証明書の添付が必要になる場合があります。
※申請地が道路、里道、水路、河川等に接する場合は官民境界確定図が必要になります。 - 地積測量図
登記する土地の位置、形状及び大きさを明確にした図面です。
土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。
手続きの流れ
何らかの事由で土地地積更生登記が必要な場合、土地地積更生登記の申請義務があります。土地家屋調査士が依頼を受けて代理人として登記申請を行います。
![]()
当事務所に土地地積更生登記の手続きのご相談又はご依頼を頂きます。その際に、できるだけ詳細な内容をお伝えして頂ければ、回答する上での参考になり、より正確なお見積りをご提示できます。なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
![]()
ご相談内容に応じ、土地地積更生登記に必要な書類をお預かり致します。
![]()
法務局、官公署等での資料調査を行います。具体的には、お預かりした資料をもとに、土地の所在地を管轄する法務局において、土地及びの登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図等を取得し、土地の概要等の確認をします。必要によっては、市区町村役場や都税事務所等での調査も必要となります。
![]()
境界確定測量により、その土地の面積を確定し、隣接土地所有者様と境界確認書を取り交わします。
![]()
資料調査・現地調査・測量をもとに、土地地積更生登記の申請書・調査報告書等の登記申請書類を作成します。
![]()
必要書類がすべて揃い、土地地積更生登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ土地地積更生登記の申請を致します。
![]()
法務局へ行き登記完了証を受け取ります。法務局の混雑状況や登記官の調査によりますが、通常は、登記申請から7日から10日程度で土地地積更生登記は完了します。ただし、境界確定測量後土地地積更生登記を申請しますので、全行程で2~4ヶ月前後の期間が必要となります。
![]()
申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。
■土地合筆登記
・数筆の「権利証」・「登記識別情報」を1つにしたい場合
・遺産相続の前提や準備として合筆する場合
土地合筆登記とは、数筆の土地を合せて、新たに一筆の土地を創設する登記をいいます。
土地合筆登記は登記記録上、数筆を一筆にするので測量は不要です。
この登記は、申請主義により所有者の自由意思によってのみされる登記ですから、所有者に申請義務はありません。
ただし、土地合筆登記には所有者や地目が同一でない場合、土地が隣接していない、担保権の設定等合併の制限がいくつかあります。
登記費用
当事務所では常に依頼者様の立場に立ち、業務の効率化を図り、高品質の成果をより負担軽減された形でご提供いたします。
なお、土地の大きさや現地の状況、必要書類の有無などにより大幅に変わってきますので、詳細はメール又はお電話などでご相談下さい。なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
※上記費用には、官公署等での調査業務、登記申請書類作成および登記申請、登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本)の取得までを含みます。
※上記費用には別途消費税がかかります。
必要書類
- 委任状
土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。 - 土地の所有権登記名義人の登記識別情報(所有権の登記済証)
所有権の登記のある土地を合筆する場合に必要になります。申請が、所有権の登記名義人本人からなされていることを登記官が確認するためです。 - 土地の所有権登記名義人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
所有権の登記のある土地を合筆する場合に必要になります。申請が、所有権の登記名義人本人からなされていることを登記官が確認するためです。
手続きの流れ
何らかの事由で土地を合筆したい場合、土地合筆登記の申請義務があります。土地家屋調査士が依頼を受けて代理人として登記申請を行います。
![]()
当事務所に土地地積更生登記の手続きのご相談又はご依頼を頂きます。その際に、できるだけ詳細な内容をお伝えして頂ければ、回答する上での参考になり、より正確なお見積りをご提示できます。なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
![]()
ご相談内容に応じ、土地合筆登記に必要な書類をお預かり致します。
![]()
法務局、官公署等での資料調査を行います。具体的には、お預かりした資料をもとに、土地の所在地を管轄する法務局において、土地及びの登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図等を取得し、土地の概要等の確認をします。必要によっては、市区町村役場や都税事務所等での調査も必要となります。
![]()
調査資料をもとに現地調査を実施、土地合筆登記できるかの判断をします。
![]()
資料調査・現地調査・測量をもとに、土地合筆登記の申請書・調査報告書等の登記申請書類を作成します。
![]()
必要書類がすべて揃い、土地地積更生登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ土地合筆登記の申請を致します。
![]()
法務局へ行き登記完了証を受け取ります。法務局の混雑状況や登記官の調査によりますが、通常は、登記申請から7日から10日程度で土地分筆登記は完了します。
![]()
申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。
■土地表題登記
・水路・道・畦畔などの国有地の払下げを受けた場合
・埋立てや河川改修等により新たに土地が生じた場合
土地の表題登記とは、登記のされていない土地について、土地の物理的な状況を、初めて登記記録の表題部を開設する登記手続きです。
物理的な状況とは、土地の所在・地番・地目・地積のことであり、これらを登記することにより、大きさや形状が明らかになります。
土地の所有者は、新たに土地が生じた日から1ヶ月以内に土地表題登記の申請義務があります。
未登記の土地を売買した方は所有権を取得したときから申請義務があります。(不動産登記法第36条)
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)
登記費用
当事務所では常に依頼者様の立場に立ち、業務の効率化を図り、高品質の成果をより負担軽減された形でご提供いたします。
土地表題登記の費用は、一般的な例(1筆で100m²ぐらいの土地の場合)で、一筆約5万円~となります。
なお、土地の大きさや現地の状況、必要書類の有無などにより大幅に変わってきますので、詳細はメール又はお電話などでご相談下さい。なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
※上記費用には、官公署等での調査業務、登記申請書類作成および登記申請、登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本)の取得までを含みます。
※上記費用には別途消費税がかかります。
※土地表題登記については、この費用以外に境界確定測量の費用がかかります。
必要書類
- 委任状
土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。 - 所有権証明書
自己の所有であることを証明する書面です。国から土地の所有権を取得したことを証する書面が必要になります。 - 土地所有者の住民票またはそれに代わる証明書
所有者を特定し、氏名及び住所を証明するために必要です。所有者が法人の場合は、当該法人の代表者事項証明書など(発行3ヶ月以内)、所有者が外国人の方は、外国人登録証明書が必要になります。 - 境界確認書
境界確定測量の段階で隣接地所有者との間で取り交わす書面です。
※法務局によっては、境界確認書に印鑑証明書の添付が必要になる場合があります。
※申請地が道路、里道、水路、河川等に接する場合は官民境界確定図が必要になります。 - 土地所在図・地積測量図
登記する土地の位置、形状及び大きさを明確にした図面です。
土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。
手続きの流れ
未登記の土地や国有地の払下げを受けた場合、土地表題登記の申請義務があります。土地家屋調査士が依頼を受けて代理人として登記申請を行います。
![]()
当事務所に土地表題登記の手続きのご相談又はご依頼を頂きます。その際に、できるだけ詳細な内容をお伝えして頂ければ、回答する上での参考になり、より正確なお見積りをご提示できます。なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
![]()
ご相談内容に応じ、土地表題登記に必要な書類をお預かり致します。
![]()
法務局、官公署等での資料調査を行います。具体的には、お預かりした資料をもとに、土地の所在地を管轄する法務局において、土地及びの登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図等を取得し、土地の概要等の確認をします。必要によっては、市区町村役場や都税事務所等での調査も必要となります。
同時に担当役所との協議を行い、その土地の所有権取得(払い下げ)は可能なのかどうかを調査します。その土地の所有権取得が可能であれば、境界確定測量の手続きに進むことになります。
![]()
境界確定測量により、その土地の面積を確定させます。実際の面積が確定されれば、土地の価格決定後、払下げ金を国に支払い、手続き終了後にその土地の所有権を取得することになります。
![]()
資料調査・現地調査・測量をもとに、土地表題登記の申請書・土地所在図・地積測量図等の登記申請書類を作成します。
![]()
必要書類がすべて揃い、土地表題登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ土地表題登記の申請を致します。
![]()
法務局へ行き登記完了証を受け取ります。法務局の混雑状況や登記官の調査によりますが、通常は、登記申請から7日から10日程度で土地表題登記は完了します。ただし、境界確定測量後土地表題登記を申請しますので、全行程で3~6ヶ月前後の期間が必要となります。
![]()
申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。
この後は、必要であれば所有権保存登記や抵当権設定登記へと進む事になります。