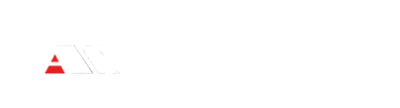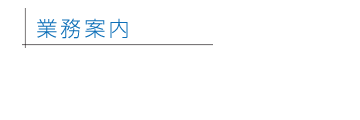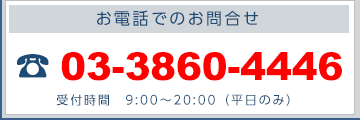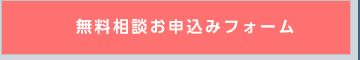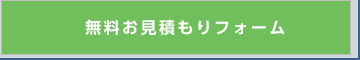■建物表題登記 ¥75,000~
・未登記の建物を購入した場合
・以前に建物を建築したが登記をしていない場合
建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。
登記簿は、「表題部」と「権利部」の2つで構成されています。「表題部」には建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・新築年月日など物理的な状況が記載され、「権利部」には所有者の住所・氏名・抵当権の設定等が記載されます。
しかし、新しく新築した建物や未登記建物には当然登記記録(登記簿)はありません。「建物表題登記」は登記記録を新たに作るための登記なのです。
なお、新築建物の所有者は、新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第47条第1項)
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)
※上記で登記記録(登記簿)は「表題部」・「権利部」で構成されていると言いましたが「表題部」に関する登記は土地家屋調査士が、「権利部」に関する登記は司法書士が代理人となって申請します。順番は「表題」→「権利」です。
登記費用
建物表題登記費用 一棟 約75,000円~
数棟同時に現地調査可能な分譲等新築建物
建物表題登記費用 一棟 約60,000円~
当事務所では常に依頼者様の立場に立ち、業務の効率化を図り、高品質の成果をより負担軽減された形でご提供いたします。
建物表題登記の費用につきましては、一般の居住用の新築建物の場合には、下記のとおりとなります。
開発行為や分譲地等で数棟同時に現地調査が可能な新築建物の場合には、現地調査の負担などが軽減されるため、
一棟約6万円~となります。
個人のお客様から一棟単体でご依頼を頂いた場合には、
一棟約7.5万円~となります。
なお、上記建物以外の場合には、建物の大きさや現地の状況、必要書類の有無などにより大幅に変わってきますので、詳細はメール又はお電話などでご相談下さい。
なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
※上記費用には、官公署等での調査業務、現地調査業務、登記申請書類作成および登記申請、登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本)の取得までを含みます。
※上記費用には別途消費税がかかります。
必要書類
- 建物所有者の住民票またはそれに代わる証明書
所有者を特定し、氏名及び住所を証明するために必要です。所有者が法人の場合は、当該法人の代表者事項証明書など(発行3ヶ月以内)、所有者が外国人の方は、外国人登録証明書が必要になります。 - 所有権証明書
建物が自己の所有であることを証明するための書面です。
申請により添付するものが異なりますが、一般的なものを挙げておきます。
1.建築確認通知書
2.建物検査済証
3.工事完了引渡証明書
4.工事代金領収書
上記以外に、所有権証明書となるものを以下に挙げます。
5.固定資産評価証明書
6.土地賃貸借契約書
7.火災保険証書
8.上申書(共有持分や、上記書類が添付することができない場合などに作成する書類。上申書には実印にて捺印して頂き、印鑑証明書の添付)
※通常は上記書類の内、2点から3点の添付があれば法務局での手続きがスムーズに行われます。 - 委任状
土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。 - 建物図面
登記する建物を特定するため、建物の位置及び形状を示した図面です。
土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。 - 各階平面図
登記する建物の床面積の範囲を特定するため、建物の各階の形状及び面積を示した図面です。
土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。
※下記必要書類は、登記の目的により必要でないものも含んでおります。
手続きの流れ
新築建物の工事が完了した場合、建物表題登記を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が建物の所有者様から依頼を受けて代理人として登記申請を行います。
![]()
当事務所に境界確定測量の手続きのご相談又はご依頼を頂きます。その際に、できるだけ詳細な内容をお伝えして頂ければ、回答する上での参考になり、より正確なお見積りをご提示できます。なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
![]()
建物表題登記に必要な書類をお預かり致します。
![]()
法務局、その他官公署等での資料調査を行います。
お預かりした資料をもとに、建物の所在地を管轄する法務局において、土地及び建物の登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図、建物図面等を取得し、記載事項に間違い及び変更がないかの確認、土地や建物の位置関係等の調査を行います。
また、場合によっては、市区町村役場や都税事務所等での調査も必要となります。
なお、調査段階において、存在しないはずの建物が登記上存在していたら建物滅失登記を、現在建物が建っている土地の地目が「畑」や「田」などであったりしたら、地目を「宅地」に変更する土地地目変更登記をする必要が出てきます。
新築建物以外の建物が同じ敷地内に存する場合、それらの建物を調査し、新築建物との位置関係等を調査する必要があります。
![]()
建物を新築する際は、建築業者などが建築確認申請手続き等を代行し、建築確認通知書が交付されます。建築確認通知書には建物の概要が記載されており、図面等も添付されています。
建物の現地調査では、この建築確認通知書及び役所での調査資料をもとに、表題登記を申請する建物が建物として登記するための要件を満たしているかを確認し、また、建物位置や形状等を調査・測量することになります。
![]()
資料調査、現地調査で得た情報をもとに、建物表題登記の申請書・建物図面・各階平面図・調査報告書等の登記申請書類を作成致します。
なお、お預かりした書類のほかに、上申書などの書類が必要な場合には、所有者様にご署名・ご捺印を頂く事になります。
![]()
必要書類がすべて揃い、建物表題登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ建物表題登記の申請を致します。
![]()
法務局へ行き登記完了証を受け取ります。法務局の混雑状況や登記官の調査によりますが、通常は、登記申請から7日から10日程度で建物表題登記は完了します。
![]()
申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。
この後は、必要であれば所有権保存登や抵当権設定登記へと進む事になります。
■建物滅失登記
・地震や火災等により建物が物理的に滅失した場合
・建物は存在しないのに登記簿だけが残っているような場合
建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。建物の登記 簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が滅失したときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第57 条)
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)
また建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容をもとに課税されます。存在しない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記は怠らないようにしてください。
登記費用
当事務所では常に依頼者様の立場に立ち、業務の効率化を図り、高品質の成果をより負担軽減された形でご提供いたします。
建物の大きさや現地の状況、必要書類の有無などにより大幅に変わってきますので、詳細はメール又はお電話などでご相談下さい。
なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
※上記費用には、官公署等での調査業務、現地調査業務、登記申請書類作成および登記申請、登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本)の取得までを含みます。
※上記費用には別途消費税がかかります。
必要書類
※下記必要書類は、登記の目的により必要でないものも含んでおります。
- 委任状
土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。 - 建物所有者の印鑑証明書
法人の場合には印鑑証明書と資格証明書(発行3ヶ月以内)が必要になります。 - 取毀し証明書
建物が滅失して存在しないことを証明するための書面です。(取毀し工事をした工事業者から発行してもらいます。これらに付随して工事業者の印鑑証明書や資格証明書なども必要になります。)
※焼失の場合は消防署の証明書が必要になります。 - 上申書
上記の書面が揃わない場合、その理由と滅失の経緯などを記載した書面が必要になります。
手続きの流れ
建物を取毀した場合や、地震や火災等により物理的に滅失した場合、建物滅失登記を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が建物の所有者様から依頼を受けて代理人として登記申請を行います。
![]()
当事務所に建物滅失登記の申請手続きのご相談又はご依頼を頂きます。その際に、できるだけ詳細な内容をお伝えして頂ければ、回答する上での参考になり、より正確なお見積りをご提示できます。なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
![]()
建物滅失登記に必要な書類をお預かり致します。
![]()
法務局、その他官公署等での資料調査を行います。
具体的には、お預かりした資料をもとに、建物の所在地を管轄する法務局において、土地及び建物の登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図、建物図面等を取得し、記載事項に間違い及び変更がないかの確認、土地や建物の位置関係等の調査を行います。
また、場合によっては、市区町村役場や都税事務所等での調査も必要となります。
![]()
役所での調査資料やご依頼者様の話をもとに、申請する建物が本当に滅失しているか否かの確認を現場にて行います。
建物の取壊し工事が完了していれば登記の申請を行うことができます。
![]()
資料調査、現地調査で得た情報をもとに、建物滅失登記の申請書・調査報告書等の登記申請書類を作成致します。
なお、お預かりした書類のほかに、上申書などの書類が必要な場合には、所有者様にご署名・ご捺印を頂く事になります。
![]()
必要書類がすべて揃い、建物滅失登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ建物滅失登記の申請を致します。
![]()
法務局へ行き登記完了証(登記済証)を受け取ります。法務局の混雑状況や登記官の調査によりますが、通常は、登記申請から7日~10日程度で建物滅失登記は完了します。
![]()
申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の閉鎖事項証明書(閉鎖謄本)をご依頼人にお渡し致します。
■建物表題部変更登記
・隣地の土地にまたがるような増築をして、建物の所在に変更が生じた場合
・建物の屋根や建物の構造体の材質を変更や増築した場合
・建物を増築や一部を取毀したりして、建物の床面積に変更が生じた場合
・附属建物を新築した場合
建物表題部変更登記とは、建物の所在・種類・構造・床面積に変更が生じた時に、登記記録(登記用紙)を現況に合致させる登記です。
なお、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第51条第1項)
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)
一方、登記手続き上の錯誤(間違い)などにより、建物の現況と登記簿上の建物の表示とが合致していない場合には、建物表題部更正登記を行い、現況に合わせた表示に「更正」することができます。変更登記が「後発的に生じた変更」に対し、更正登記は「当初からの不一致」ということになります。
登記費用
建物の床面積の変更などの図面作成が必要な登記の場合
建物表題部変更登記費用 一棟約60,000円~
当事務所では常に依頼者様の立場に立ち、業務の効率化を図り、高品質の成果をより負担軽減された形でご提供いたします。
建物表題部変更登記の費用につきましては下記のとおりとなります。
建物の種類変更などの図面作成が必要ない登記の場合には、約3万円~となります。
建物の床面積の変更などの図面作成が必要な登記の場合には、約6万円~となります。
建物の大きさや現地の状況、必要書類の有無などにより大幅に変わってきますので、詳細はメール又はお電話などでご相談下さい。
なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
※上記費用には、官公署等での調査業務、現地調査業務、登記申請書類作成および登記申請、登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本)の取得までを含みます。
※上記費用には別途消費税がかかります。
必要書類
※下記必要書類は、登記の目的により必要でないものも含んでおります。
- 建物所有者の住民票またはそれに代わる証明書
所有者を特定し、氏名及び住所を証明するために必要です。所有者が法人の場合は、当該法人の代表者事項証明書など(発行3ヶ月以内)、所有者が外国人の方は、外国人登録証明書が必要になります。 - 委任状
土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。 - 所有権証明書
増築部分が自己の所有であることを証明するための書面です。※建物表題部変更登記の場合、その変更内容によっては、所有権証明書の添付が必要ない場合もあります。 - 変更を証する書面
種類変更であれば、変更後の種類を特定できるような建築確認通知書などの書面や、リフォーム業者様からの証明書などが必要となる場合があります。 - 建物図面
変更(更正)する建物を特定するため、建物の位置及び形状を示した図面です。
土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。 - 各階平面図
変更(更正)する建物の床面積の範囲を特定するため、建物の各階の形状及び面積を示した図面です。
土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。
手続きの流れ
上記の工事が完了した場合、建物表題部変更登記を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が建物の所有者から依頼を受けて代理人として登記申請を行います。
![]()
当事務所に建物表題部変更登記の申請手続きのご相談又はご依頼を頂きます。その際に、できるだけ詳細な内容をお伝えして頂ければ、回答する上での参考になり、より正確なお見積りをご提示できます。なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
![]()
建物滅失登記に必要な書類をお預かり致します。
![]()
法務局、その他官公署等での資料調査を行います。
具体的には、お預かりした資料をもとに、建物の所在地を管轄する法務局において、土地及び建物の登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図、建物図面等を取得し、記載事項に間違い及び変更がないかの確認、土地や建物の位置関係等の調査を行います。
また、場合によっては、市区町村役場や都税事務所等での調査も必要となります。
![]()
建物の現地調査では、調査資料や依頼者様の話をもとに、依頼物件が本当に変更を生じているかを調査し、建築確認通知書等の図面を元に建物の変更箇所を調査・測量します。
変更内容によっては図面がない場合もありますので、その場合は独自に調査をします。
![]()
資料調査、現地調査で得た情報をもとに、建物表題部変更登記の申請書・建物図面・各階平面図・調査報告書等の登記申請書類を作成致します。
なお、お預かりした書類のほかに、上申書などの書類が必要な場合には、所有者様にご署名・ご捺印を頂く事になります。
![]()
必要書類がすべて揃い、建物表題部変更登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ建物表題部変更登記の申請を致します。
![]()
法務局へ行き登記完了証(登記済証)を受け取ります。法務局の混雑状況や登記官の調査によりますが、通常は、登記申請から7日~10日程度で建物表題部変更登記は完了します。
![]()
申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。
■区分建物表題登記
・二世帯住宅や店舗併用住宅などで、要件を満たす複数の建物としたい場合
区分建物表題登記とは分譲マンション等の区分建物を新築した時にする登記です。分譲マンションなど1棟に数戸の専有部分がある時は、各々の専有部分について登記申請ができます。
一戸建の建物表題登記と同じく、区分建物についての物理的な状況(所在・名称・家屋番号・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を、登記簿に登録する登記手続きで建物の大きさや形状等が公示されます。
また、区分建物表題登記では、物理的状況に加えて、敷地の権利による割合や規約による共用部分なども登記されることがあります。
原始取得者(分譲マンション等を建てた会社等)は、建物の新築後1ヶ月以内に区分建物表題登記の申請義務があります。(不動産登記法第47条第1項)この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)
一戸建の二世帯住宅等で区分登記をすると相続等で係争の場合、権利の設定や移転が可能になる場合があるので注意が必要です。
登記費用
当事務所では常に依頼者様の立場に立ち、業務の効率化を図り、高品質の成果をより負担軽減された形でご提供いたします。
建物の大きさや現地の状況、必要書類の有無などにより大幅に変わってきますので、詳細はメール又はお電話などでご相談下さい。
なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
※公正証書などで規約を設定する場合には別途作成費がかかります。
※上記費用には、官公署等での調査業務、現地調査業務、登記申請書類作成および登記申請、登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本)の取得までを含みます。
※上記費用には別途消費税がかかります。
必要書類
- 建物所有者の住民票またはそれに代わる証明書
所有者を特定し、氏名及び住所を証明するために必要です。所有者が法人の場合は、当該法人の代表者事項証明書など(発行3ヶ月以内)、所有者が外国人の方は、外国人登録証明書が必要になります。 - 所有権証明書
建物が自己の所有であることを証明するための書面です。
申請により添付するものが異なりますが、一般的なものを挙げておきます。
1.建築確認通知書
2.建物検査済証
3.工事完了引渡証明書
4.工事代金領収書
上記以外に、所有権証明書となるものを以下に挙げます。
5.固定資産評価証明書
6.土地賃貸借契約書
7.火災保険証書
8.上申書(共有持分や、上記書類が添付することができない場合などに作成する書類。上申書には実印にて捺印して頂き、印鑑証明書の添付)
※通常は上記書類の内、2点から3点の添付があれば法務局での手続きがスムーズに行われます。 - 委任状
土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。 - 建物図面
登記する建物を特定するため、建物の位置及び形状を示した図面です。
土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。 - 各階平面図
登記する建物の床面積の範囲を特定するため、建物の各階の形状及び面積を示した図面です。
土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。
※規約を定めた場合には、公正証書などの規約を証する書面の添付が必要になります。
※下記必要書類は、登記の目的により必要でないものも含んでおります。
手続きの流れ
新築建物の工事が完了した場合、区分建物表題登記を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が建物の所有者様から依頼を受けて代理人として登記申請を行います。
![]()
当事務所に境界確定測量の手続きのご相談又はご依頼を頂きます。その際に、できるだけ詳細な内容をお伝えして頂ければ、回答する上での参考になり、より正確なお見積りをご提示できます。なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
![]()
区分建物表題登記に必要な書類をお預かり致します。
![]()
法務局、その他官公署等での資料調査を行います。
お預かりした資料をもとに、建物の所在地を管轄する法務局において、土地及び建物の登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図、建物図面等を取得し、記載事項に間違い及び変更がないかの確認、土地や建物の位置関係等の調査を行います。
また、場合によっては、市区町村役場や都税事務所等での調査も必要となります。
なお、調査段階において、存在しないはずの建物が登記上存在していたら建物滅失登記を、現在建物が建っている土地の地目が「畑」や「田」などであったりしたら、地目を「宅地」に変更する土地地目変更登記をする必要が出てきます。
新築建物以外の建物が同じ敷地内に存する場合、それらの建物を調査し、新築建物との位置関係等を調査する必要があります。
![]()
区分建物を新築する際は、建築業者などが建築確認申請手続き等を代行し、建築確認通知書が交付されます。建築確認通知書には建物の概要が記載されており、図面等も添付されています。
建物の現地調査では、この建築確認通知書及び役所での調査資料をもとに、表題登記を申請する建物が区分建物として登記するための要件を満たしているかを確認し、また、建物位置や形状等を調査・測量することになります。
![]()
資料調査、現地調査で得た情報をもとに、建物表題登記の申請書・建物図面・各階平面図・調査報告書等の登記申請書類を作成致します。
![]()
必要書類がすべて揃い、建物表題登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ区分建物表題登記の申請を致します。
![]()
法務局へ行き登記完了証を受け取ります。法務局の混雑状況や登記官の調査によりますが、通常は、登記申請から7日から14日程度で建物表題登記は完了します。
![]()
申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。
この後は、必要であれば所有権保存登や抵当権設定登記へと進む事になります。
■その他の建物登記
建物分割登記
効用上一体として利用される状態にある数棟の建物が一個の建物(主たる建物と同一の登記記録(登記用紙)に登記されている従たる附属建物)を、物理的形状又は位置関係には何らの変更を加えることなく、登記記録(登記用紙)上別個独立の建物とする登記を建物分割登記といいます。
この登記は、申請主義により所有者の自由意思によってのみされる登記ですから、所有者に申請義務はありません。
たとえば、附属建物を他人に賃貸したとしても、所有者に分割する意思がなければ、分割登記を申請する必要はありません。
これに対して、附属建物を他人に売買し、所有権を移転する場合は、その前提として建物の分割登記を申請する必要があります。
建物の一部を取り毀すなどして、数棟の建物にすることを「分棟」といいます。この「分棟」には、2通りあります。
① 分棟後の建物に主従の関係が生じる場合は、分棟した建物を附属建物とする建物表題部変更登記を申請します。
② 分棟後の建物を登記簿上別個独立の建物とする場合は、分棟した建物を別個独立の建物とする建物分棟・分割登記を申請します。建物分棟・分割登記は、物理的形状変更をする点で建物の分割登記とは異なります。
建物合併登記
登記記録上それぞれ別個の建物において、物理的に変更を加えることなく、ある建物を他の建物の附属建物とする登記を建物合併登記といいます。
合併登記後の数個の建物には効用上一体として利用される主従の関係が成立していなければなりません。
建物の「合体」と類似されがちですが、合併の方は物理的な変更を加えず登記簿上1個の建物とし、所有者に申請義務がない点で建物の合体とは異なります。
この登記は、申請主義により所有者の自由意思によってのみされる登記ですから、所有者に申請義務はありません。
ただし、建物を合併する場合には合併制限があります。これに違反する建物の合併登記の申請は、不動産登記法第25条第2号の規定により却下されます。
合併制限に抵触するものとしては下記のようなものがあります。
① 効用上一体として利用される関係にない建物の合併
合併登記は、ある建物を他の建物の附属建物とする性質のものですから、主従の関係にないときは、合併登記することができません。
② 所有者の異なる建物の合併
所有者の異なる合併登記を認めると、合併後の各所有者の権利関係の公示が困難になるからです。
所有者が同一の場合であっても、それぞれの土地の登記記録(登記用紙)に記録された住所が異なる場合は「所有者が異なる」ものとして扱われます。この場合には、住所変更の登記も併せて申請しなければなりません。
③ 共有者の持分割合が異なる建物の合併
共有の建物の場合は、②に記載したとおり、各共有者が同一でも、持分割合が異なる場合は合併登記することができません。
④ 所有権の登記のある建物と所有権の登記のない建物の合併
このような合併は登記上権利関係を錯雑、不明確にし、また所有者が同一でも所有権の有無の合併は合併後の建物の一部につき所有権の登記がなされる不都合な結果を生じるので合併登記することができません。
⑤ 共用部分たる旨の登記又は団地共用部分たる旨の登記のある建物の合併
当該建物が共用部分又は団地共用部分であることを第三者に対抗するための特別な登記であり、専有部分と一体的に処分されるので、単体で合併登記をすることはできません。
⑥ 所有権の登記以外の権利に関する登記のある建物の合併
ただし、建物につき先取特権、抵当権、質権に関する登記で、登記原因・登記日付・登記の目的及び受付番号が同一であれば、合併は可能です。
建物合体登記
登記記録上、互いに主従の関係にない独立した建物が、増築等の工事により構造上一個の建物となることを建物の合体といいます。建物の合体は数個の建物に物理的な変更を加えて1個の建物とする点で、建物の「合併」とは異なります。
合体する建物の所有者は、建物が合体した日から1ヶ月以内に建物の合体の登記の申請義務があります。(不動産登記法第49条第1項)
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)
また、建物の合体の登記は次の6通りあります。
① 未登記の建物と未登記の建物を合体した場合
→建物の表題登記
② 未登記の建物と表題登記のみされた建物を合体した場合
→合体による建物表題登記及び合体による建物表題登記の抹消
③ 未登記の建物と所有権の登記のある建物を合体した場合
→合体による建物表題登記及び合体による建物表題登記の抹消並びに合体後の建物につき所有権保存登記
④ 表題登記のみされた建物と表題登記のみされた建物を合体した場合
→合体による建物表題登記及び合体による建物表題登記の抹消
⑤ 表題登記のみされた建物と所有権の登記のある建物を合体した場合
→合体による建物表題登記及び合体による建物表題登記の抹消並びに合体後の建物につき所有権保存登記
⑥ 所有権の登記のあると所有権の登記のある建物を合体した場合
→合体による建物表題登記及び合体による建物表題登記の抹消
建物合体登記申請は高度な専門知識が必要になり、建築図面・建物調査・建物に関する図面作成・各種書類の作成などが必要になります。可能な限り事前に土地家屋調査士にご相談し、申請手続きのご依頼をお勧めいたします。
建物区分登記
一棟の建物を、登記記録上、数個の建物とする目的で区分し、その部分を独立した所有権の目的とするための登記を建物区分登記といいます。
例えば、1つの建物として登記がされている賃貸マンションを分譲目的に、いくつかの区分所有建物として登記したい場合などに登記を行います。
この区分される建物の部分は「構造上の独立性」及び「利用上の独立性」の要件が必要になります。
この登記は、申請主義により所有者の自由意思によってのみされる登記ですから、所有者に申請義務はありません。
建物区分登記申請は高度な専門知識が必要になり、建築図面・建物調査・建物に関する図面作成・各種書類の作成などが必要になります。可能な限り事前に土地家屋調査士にご相談し、申請手続きのご依頼をお勧めいたします。